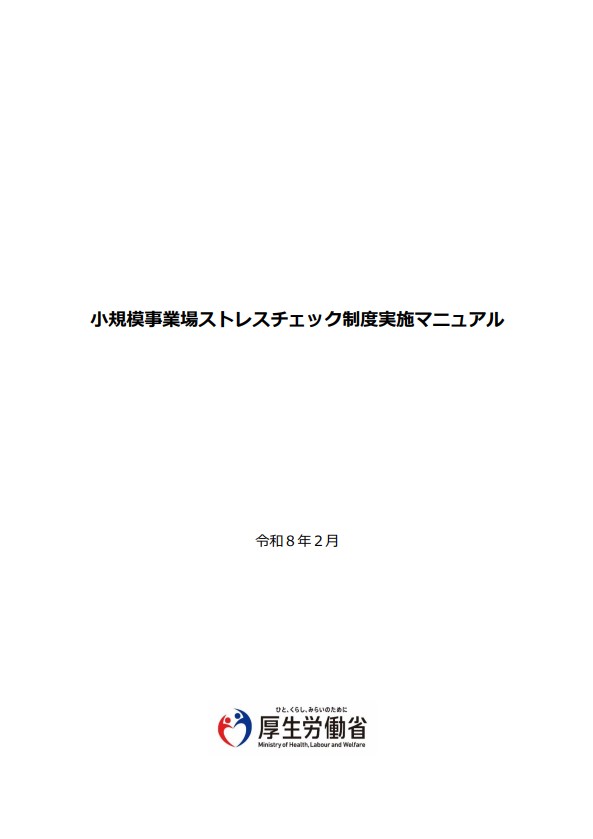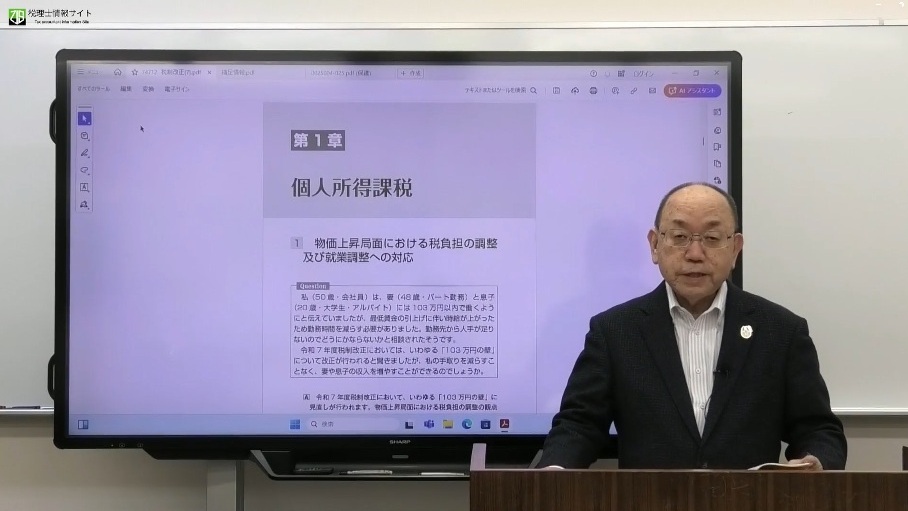「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されています
2月26日、厚生労働省は、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。
50人未満の事業場におけるストレスチェック義務は、令和7年改正安衛法により、「公布後3年以内に政令で定める日」より施行されますが、改正に対応できるよう、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成等を行うこととされ、検討が進められてきました。
次のような構成となっており、50人未満の事業場におけるストレスチェックについては、「原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨され」ていることから、従来のストレスチェックマニュアル(『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』)にはない「8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点」が設けられています。
1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備
2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
3 ストレスチェックの実施
4 医師の面接指導及び事後措置
5 集団分析・職場環境改善
6 労働者のプライバシーの保護
7 不利益取扱の禁止
8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点
巻末資料① ストレスチェック制度実施規程(モデル例)
巻末資料② サービス内容事前説明書(モデル例)
巻末資料③ 職業性ストレス簡易調査票
巻末資料④ 関係法令・各種情報等
巻末資料の規程例においても、外部委託を想定して作成されているため、従来のストレスチェックマニュアルと比較すると、実施体制に関する規定で次のような違いがあります。
【小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル】
第2章 実施体制
(ストレスチェックの委託先)
第2条 ストレスチェックは、外部機関に委託して実施する。
(実務担当者)
第3条 委託先の外部機関との連絡調整、会社におけるストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当する実務担当者は、 課職員とする。
2 実務担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法により社員に周知する。また、人事異動等により実務担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により社員に周知する。
(ストレスチェックの実施者及び実施事務従事者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、委託先の外部機関において選任された医師・保健師等とする。
2 ストレスチェックの実施事務従事者は、委託先の外部機関において選任された者とし、実施者の指示のもと、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
3 実施者及び実施事務従事者は、個人のストレスチェック結果等の健康情報を取り扱うことから、労働安全衛生法により守秘義務が課せられていること。
(面接指導を担当する医師)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、外部の面接指導を担当する医師(以下 面接指導担当医師」という。)に依頼して実施する。
【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル】
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、 課職員とする。
2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法により、社員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により社員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、会社の産業医及び保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び 課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 衛生管理者又は 課の職員であっても、社員の人事に関して権限を有する者(課長、調査役、 )は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社の産業医が実施する。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。