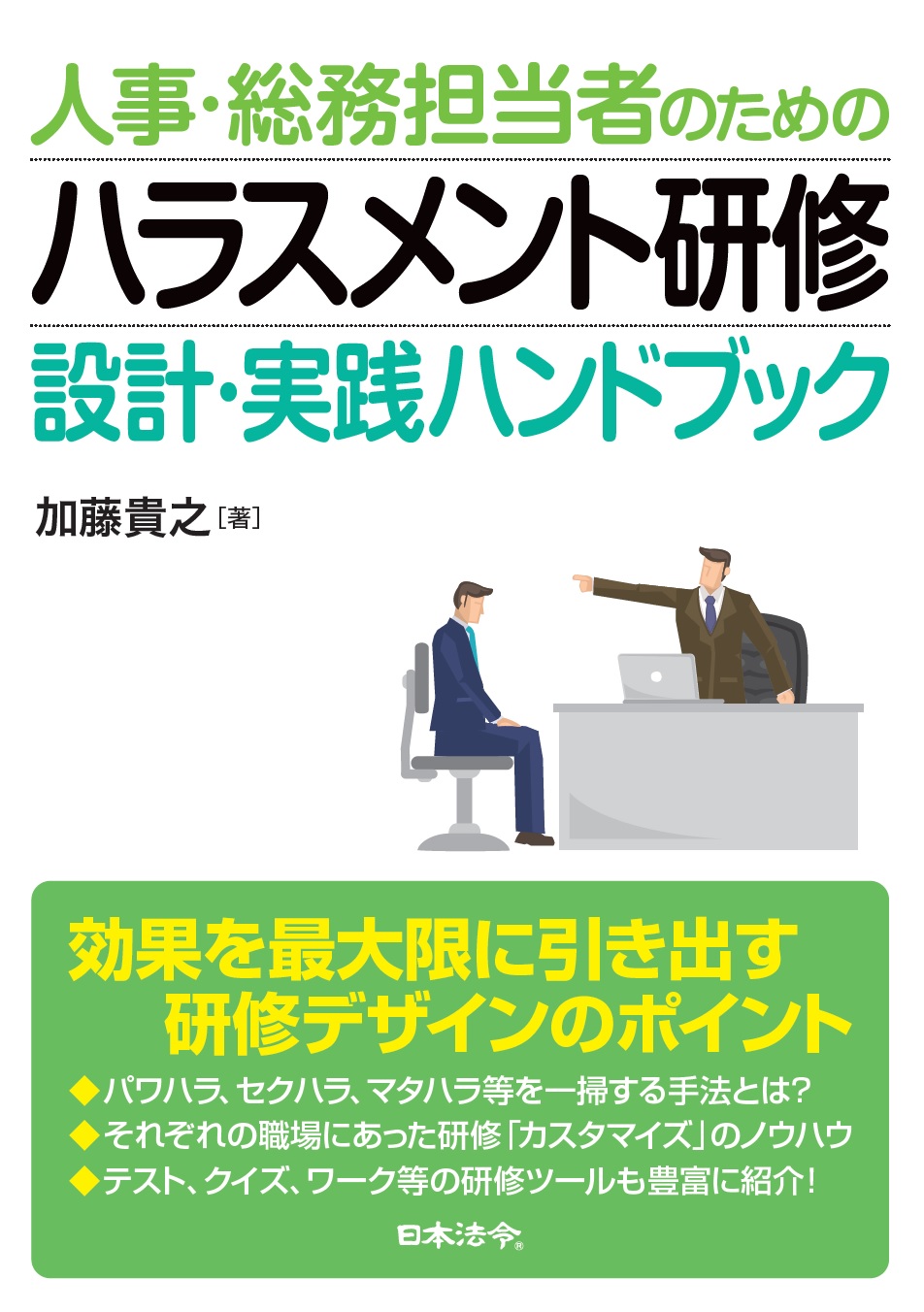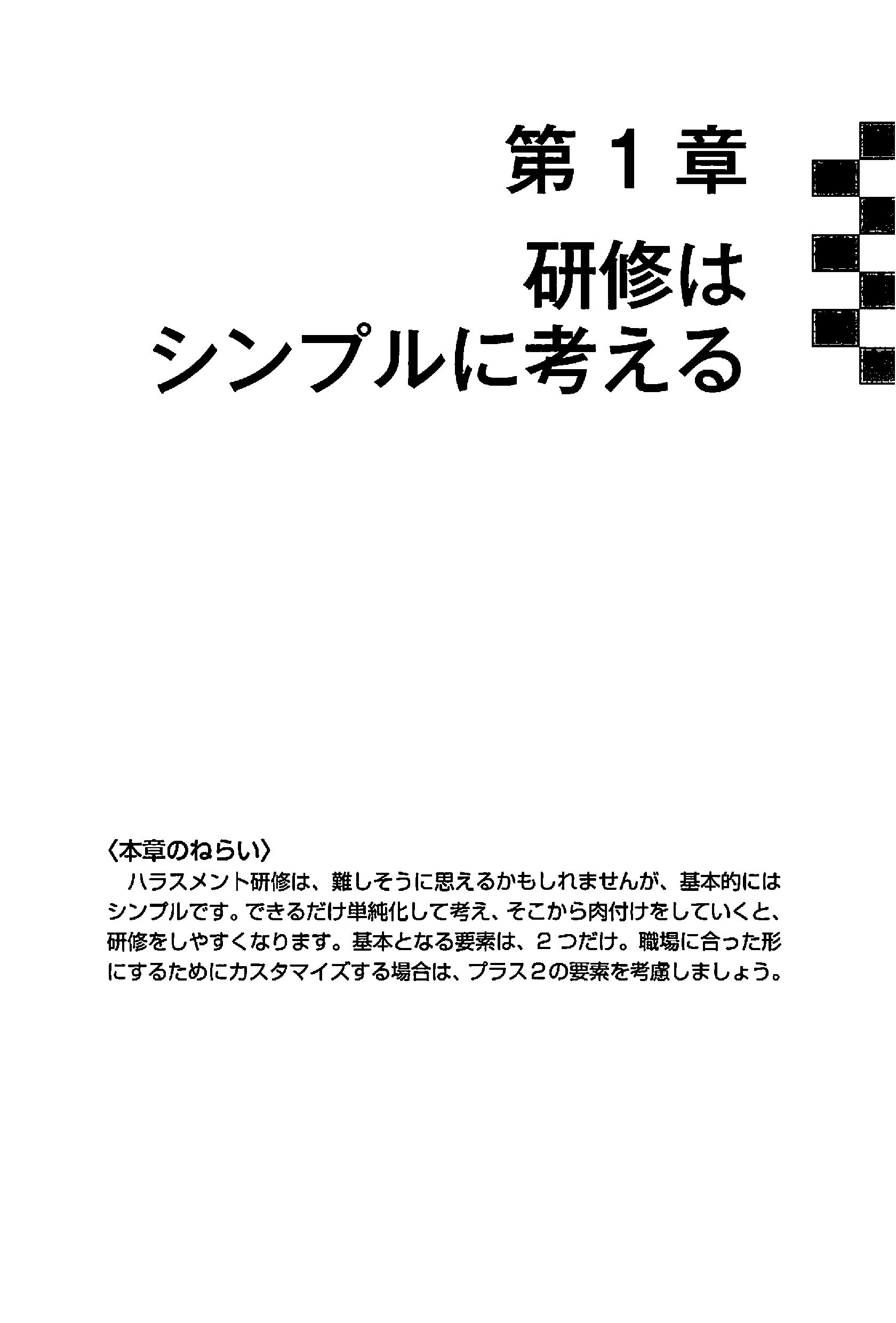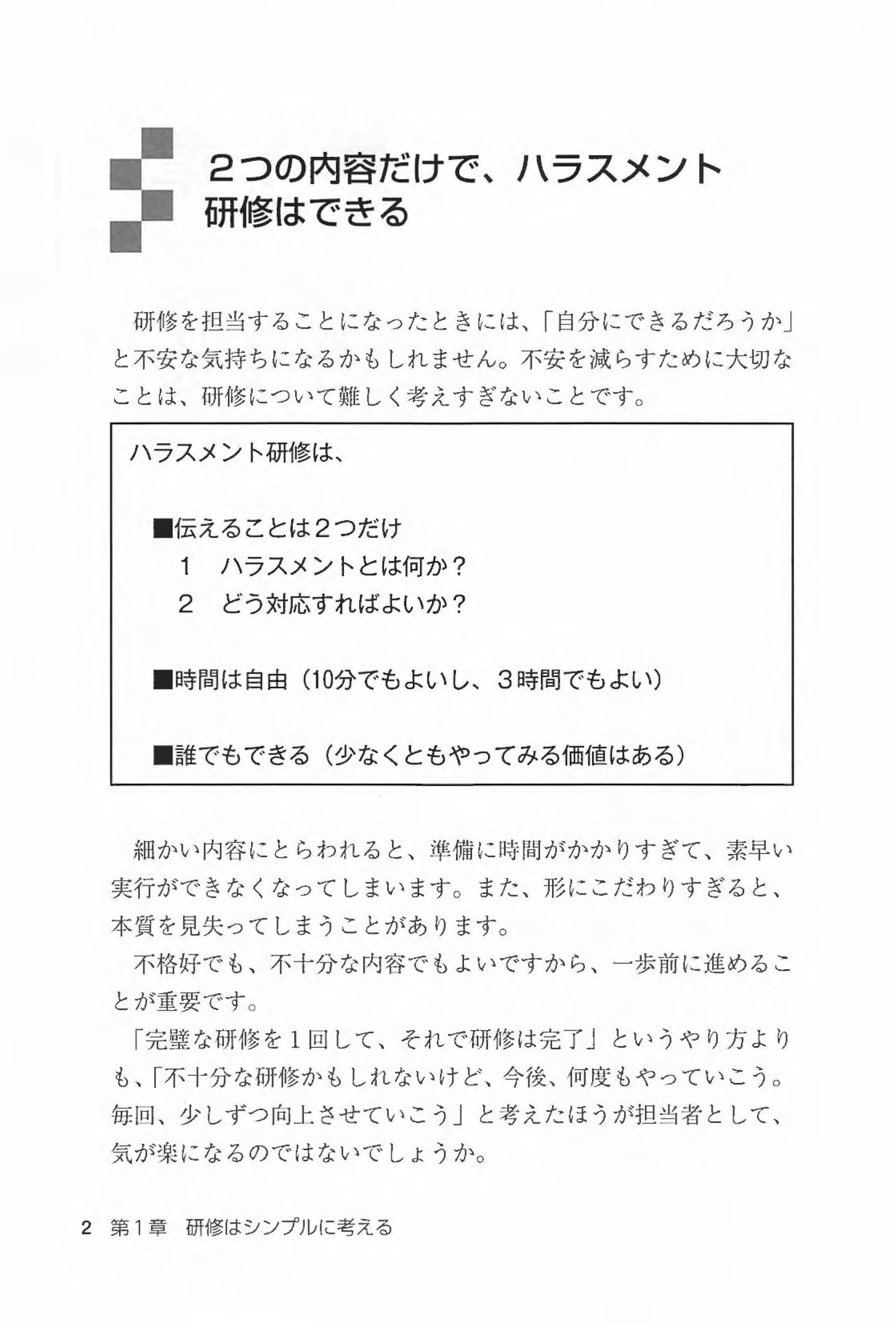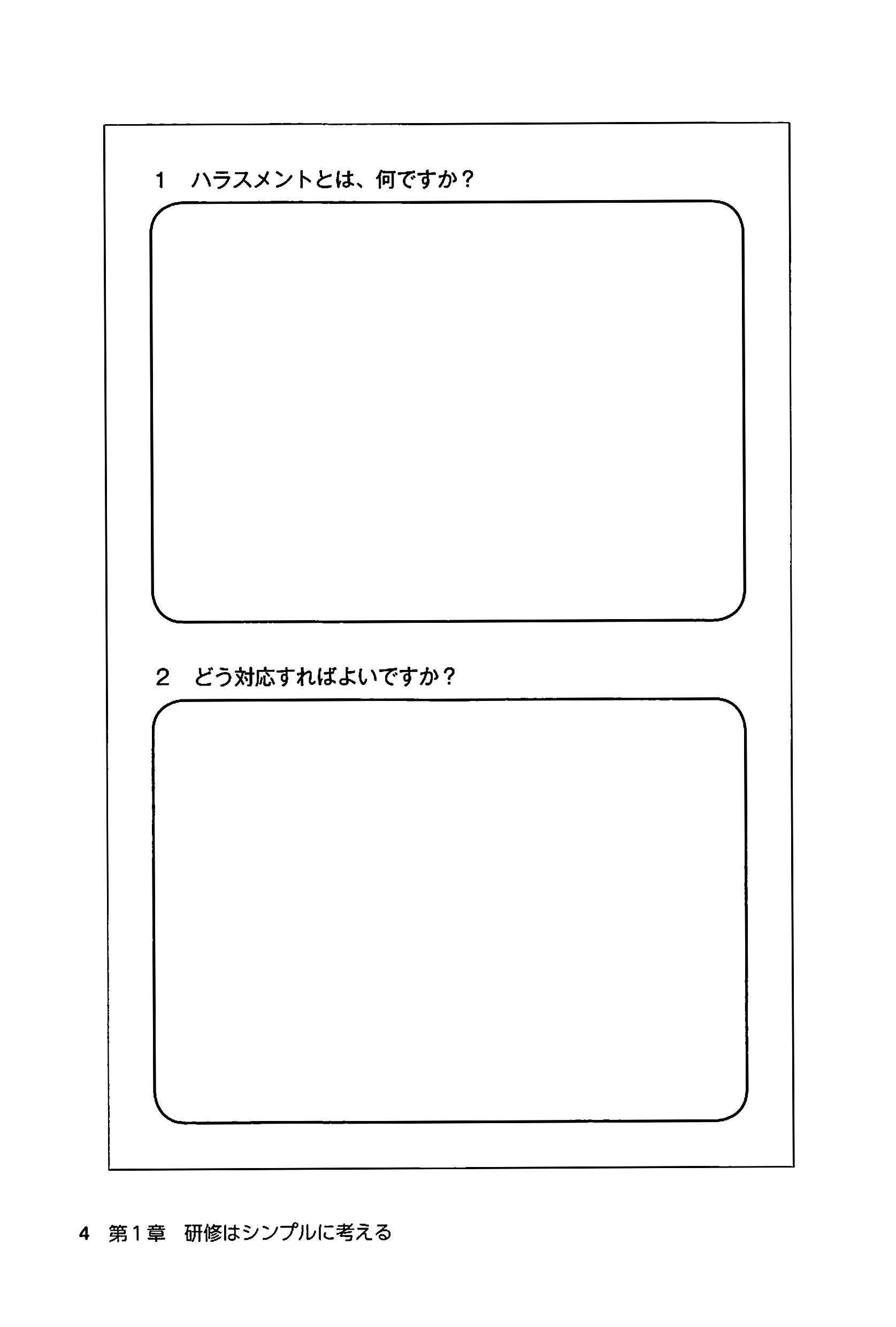商品詳細Merchandise
人事・総務担当者のためのハラスメント研修 設計・実践ハンドブック
概要
効果を最大限に引き出す研修デザインのポイント
◆パワハラ、セクハラ、マタハラ等を一掃する手法とは?
◆それぞれの職場にあった研修「カスタマイズ」のノウハウ
◆テスト、クイズ、ワーク等の研修ツールも豊富に紹介!
パワハラ防止法制が令和2年6月からスタート。このタイミングに合わせて、従業員へのパワハラ研修を予定している企業も多いようです。
しかし、パワハラを含むハラスメントの態様は、企業の規模や業種、個別的環境によって大きく異なり、一律の「教科書的な」研修を行っても、ほとんど防止効果は見込めません。自社の実態や実例に合わせ、それを徹底的に分析・検討した上で対策をとることが重要です。
また、ハラスメントとなることを恐れるあまり、社員教育やコミュニケーションが不能になってしまうケースもあります。
こうしたマイナス効果を抑えつつ、効果的な研修を行うことが人事・総務部門の今後のミッションとなってくるでしょう。
そこで本書では、さまざまなハラスメントを解決するための「効果を引き出す」研修をデザインし、実践する際のポイントを解説します。
詳細
[著者略歴]
加藤 貴之〔かとう・たかゆき〕
1962年生。早稲田大学卒。米経済誌『フォーブス』日本版編集部勤務後、情報サイト「ストレスケア・コム」設立。日本産業カウンセリングセンターコンサルタントを経て、2000年から(株)メンティグループ代表取締役コンサルタント。「組織コミュニケーション」の観点から企業・官公庁のパワハラ対策に携わり、1万人を超える人にパワハラ研修を行う。
著書:『ストレス解消ハンドブック』(PHP研究所) 監修ビデオ:『メンタルケアの聞く技術』『セクハラ相談 加害者ヒアリングの進め方』(以上、日本経済新聞出版社)、『メンタルヘルスケア実践のポイント』(PHP研究所)、『上司が萎縮しないパワハラ対策』(日本法令)。
[目次]
第1章 研修はシンプルに考える
□2つの内容だけで、ハラスメント研修はできる
□研修は「判断力」と「対応力」を高めてもらうもの
□研修で大切な「リテンション」と「トランスファー」
□職場に合わせて「カスタマイズ」する
□研修の目的は「備えること」
□たった2つのことを再確認する
第2章 研修の準備をする
□研修時間の目安はどのくらい?
□研修会場のレイアウトは?
□10分ごとのモジュールをつくる
□練習は声に出すのは数回、あとは頭の中でやる
□レジュメ・配付資料はどんなものにする?
□どんなスライドがよいか?
□質問にどう備えておくか?
□受講者のニーズを探ることも重要な準備
□「ブリーフィング」という方法でもよい
□ウェブ研修という方法もある
□どんな情報源から情報を集めればよい?
第3章 法律と指針を確認しておく
□4つのハラスメントの法律を確認しておく
□4つの指針について知っておく
□4つの指針における各ハラスメントの「定義」は?
□4つの指針でわかるハラスメントの全体構造
□指針で求められている措置は、10又は11項目
□4つの指針の相談後の対応の違いを比較する
第4章 ハラスメントとは何か?
□ハラスメントは、一方的な言動で起こる
□パワーハラスメントとは何か?
□「オセロ」のようなイメージ
□「置き換えテスト」を使って考えてみる
□パワハラによって生じるダメージとは?
□「厚労省の企業名公表」より怖い「SNSの企業名公表」
□パワハラが起こると「情報」が上がってこなくなる
□パワハラはものを言えない職場で起こりやすい
□パワハラ対策の管理職にとってのメリットは?
□「よりよいマネジメント」を考えるだけでよい
□パワハラ対策の全体像と相場観をつかんでおく
□「パワハラのトライアングル」を意識した研修デザインも
□社内ルールの確認は研修に必ず入れる
□「監督責任」の研修がパワハラ防止のカギを握る
□セクシュアルハラスメントとは何か?
□マタニティハラスメントとは何か?
□シンプルな防止策は、「相手の話を聞くこと」
第5章 どう対応したらよいか?
対 応 編
□ハラスメントを受けたら?…相談する
□ハラスメントを受けたら?…距離をとる
□同僚として相談を受けたら?
□上司として相談を受けたら?
□ハラスメントを目撃したら?
□ハラスメントをしてしまったと思ったら?
□部下のハラスメントに気付いたら?
コミュニケーション編
□「短いコミュニケーション」を増やす
□双方向のコミュニケーションにする
□「さん付け」で名前を呼ぶ
□叱る前に「予告」をしておく
□叱る目的をはっきりさせる
□「ねぎらい」の言葉を増やす
□フェイルセーフ状態をつくっておく
□「ワン・オン・ワン・ミーティング」をする
□「プッシュ型」から「プル型」へ
□「3秒間の沈黙」をつくる
□「インターチェンジ」を増やす
□部下等からリスク情報を早めに伝える
□部下等からホウレンソウの「相談」を使う
□部下等から上司や先輩に話しかける
指 導 編
□家を建てるためにレンガを積め
□結果が出るまでの「タイムラグ」を見込んでおく
□結果が出ない人には、プロセスの改善にフォーカスする
□アドバイスをしてくれる人を持つ
判 断 編
□「他の人だったら…?」と考える
□「自分だったら…?」と考える
□「より良いマネジメントはないか?」と考える
第6章 研修用ツールを作り、ワークを取り入れる
□研修用ツールを作り、ワークを取り入れる
□就業規則から「テスト」を作る
□4つの指針から「テスト」を作る
□アンケート結果を「クイズ」にする
□その場で「クイズ+実態調査」をする
□研修用ビデオを使って、ディスカッション
□「簡易チェックリスト」を用意しておく
第7章 研修デザインの参考例
□研修の組立て方は、最小から増やしていく
□相手に合わせて2つの内容を配分する
□パワハラ、セクハラ、マタハラのどれにウエイトを置くか
□10分単位のモジュールを作っておいて組み立てる