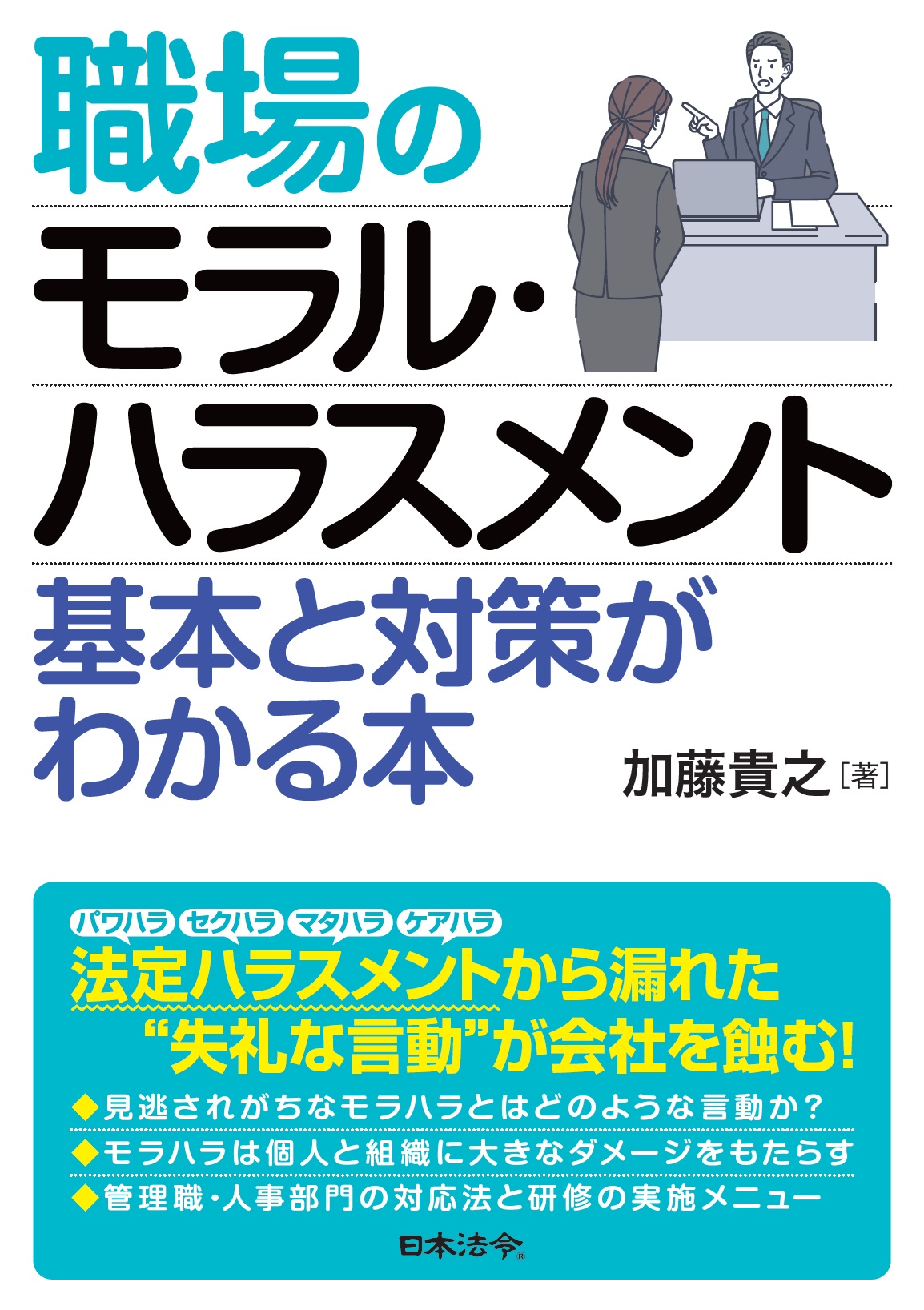商品詳細Merchandise
職場のモラル・ハラスメント 基本と対策がわかる本
概要
法定ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ・ケアハラ)から漏れた“失礼な言動”が会社を蝕む!
◆見逃されがちなモラハラとはどのような言動か?
◆モラハラは個人と組織に大きなダメージをもたらす
◆管理職・人事部門の対応法と研修の実施メニュー
モラル・ハラスメントは、ハラスメントに至る前の「失礼な言動」の集積です。それ自体には法的な定義がなく、パワハラ、セクハラ、マタハラ、ケアハラのように対策が義務づけられていないだけに、ある意味法定ハラスメントよりも扱いが難しいです。
ひとつひとつの言動そのものはハラスメントと呼ぶほどでもないため、発見や対応が遅れがちなのもモラハラの特徴です。
そこで本書では、そうした見逃されがちなハラスメントを可視化し、職場におけるモラハラの発現とその影響について分析するとともに、管理職や人事部門における対応方法や防止のための研修の進め方を紹介していきます。
詳細
[著者略歴]
㈱メンティグループ代表取締役コンサルタント。主に企業向けのハラスメント対策のコンサルティングや講演・研修を行うほか、国税局、警察本部、自衛隊等でも研修を行い、研修受講者は1万人を超える。
著書:『ハラスメント研修 設計・実践ハンドブック』(日本法令)、『上司が萎縮しないパワハラ対策』(日本法令)、『ストレス解消ハンドブック』(PHP研究所)ほか。
[目次]
第1章 見逃されているハラスメントがある
■どのカテゴリーにも当てはまらないハラスメントも
■典型的なパワハラと、パワハラとは言いがたいケース
■セクハラのケースと、セクハラとは言いがたいケース
■ケアハラのケースと、ケアハラとは言いがたいケース
■「バーバルなハラスメント」と「ノンバーバルなハラスメント」
■「アクティブなハラスメント」と「パッシブなハラスメント」
■典型的なパターン以外のハラスメントも多い
■「失礼なことをされた」という段階で介入する
第2章 職場のモラル・ハラスメントとは何か?
■家庭内で起こっているモラル・ハラスメント
■モラル・ハラスメントは職場でも起こる
■モラル・ハラスメントの定義は?
■ハラスメントは、もともとは軍事用語
■「繰り返し」によって何が起こるのか?
■何度も繰り返すと、ポジティブなこともネガティブになる
■1回でも悪質な行為が含まれるようになった
■モラハラにつながり得る「失礼な言動」とは?
■モラハラとその他のハラスメントの要素は共通している
■ハラスメントかどうかの確実な判断は誰にもできない
第3章 モラハラは個人と組織に大きなダメージをもたらす
■モラハラで精神が消耗してしまう
■モラハラは敏感にさせられた状態
■何度も思い出すたびにつらくなる
■思い出すことで、心身症やうつにもなる
■モラハラでPTSDになることも
■家族や友人との人間関係を壊してしまう
■モラハラで注意散漫になりミスが起こりやすくなる
■モラハラで注意がそれてパフォーマンスが下がる
■モラハラでミスが隠される恐れも
■モラハラで欠勤、離職が増える
■モラハラは周囲の人に与える影響も大きい
第4章 インフォーマルな対応を活用する
■フォーマルな対応とインフォーマルな対応がある
■「早期のインフォーマルな対応」が推奨されている
■すみやかに被害を防ぐために
■なぜ、初期段階でフォーマル対応をするとこじれるのか?
■恨みのような気持ちが出てくる前に
■インフォーマルな対応の手順
■インフォーマル対応では、オープンな形は避ける
■フォーマルな対応の手順
■どちらの対応を望んでいるかを確認する
■インフォーマル対応のメモの取り方
■相談記録の情報管理をアップデートする
第5章 モラハラを受けたときの対応法
■モラハラを受けたときは……
■失礼なことを1週間に複数回されたら申し出てよい
■上司や同僚への相談の仕方
■モラハラ相談は、最初はインフォーマル対応になる
■相談窓口に相談する場合はメモをとっておく
■出来事より働きにくさを伝える
■対応してくれた人にお礼を言う
■同僚として相談を受けた場合の対応法
■相談窓口までエスコートする
■第三者として相談する
第6章 管理職はどのように対応すべきか?
■初期段階では管理職の役割が大きい
■心理的安全性の高い職場づくりが前提
■心理的安全性の高い時間帯を作る
■インフォーマルな1on1も行う
■1on1は、ねぎらいの言葉から入る
■職場環境のことも聞いてみる
■大したことはないという過小視をしない
■先を急がず話をよく聞く
■最後の5分に集中して話を聞く
■話してくれたことにお礼を言う
■「大切にされている」と思ってもらえる対応をする
■相談者の意向を確認する
■行為者へは改善を促す
■「謝りたい」という人には場を設ける
■調整には、セパレートの考え方も大切
■相談者に進捗状況をフィードバックする
■アクティブなモニタリングを行う
■経過観察はポイントを絞ってよく見る
■難しい案件は抱え込まず、人事部門に相談する
第7章 人事部門はどのように対応すべきか?
■人事部門におけるハラスメント対策の始まり
■離職防止のための相談から出てきたセクハラ相談のノウハウ
■日本企業の中で続いたセクハラ問題への試行錯誤
■アメリカ発のニュースで、セクハラ問題が重要な経営課題に
■心理面に配慮しない対応が問題をこじらせてしまった
■エモーショナルな対応の重要性が認識され始めた
■新たにパワハラへの対応が必要になった
■対応しないことによるリスクが大きくなっていった
■心のケアのためにエモーショナルな対応を優先する
■相談窓口をヘルプラインにする
■メールなどでの匿名相談も受け付ける
■モラハラ後の処分をどうするか
■エグジット・インタビューでリスクを防ぐ
第8章 モラハラ防止のためのコミュニケーション研修
■研修でコミュニケーションを向上させる
■双方向のコミュニケーションにするための方法
■失礼なことをしないようにする
■失礼なことをしてしまったら、謝る
■ワーク1 視線を合わさないで会話をする
■ワーク2 視線を合わさない挨拶を自撮りする
■ワーク3 聞く姿勢がある場合とない場合の違いを考える
■ワーク4 失礼な言動について話し合う
■ワーク5 後輩指導について考える
■ワーク6 管理職の相談対応について考える
■ワーク7 行為者への指導について考える
■ワーク8 フィードバック(管理職)について考える
■ワーク9 謝罪への立会い(管理職)について考える
■研修のワーク部分の設計例
第9章 離職を防ぐためにできること
■離職に至るメカニズムを知っておく
■①離職要因の研究から出てきたバーンアウト
■②ストレスの理論を整理したCOR理論
■③離職を防ぐためのJD-Rモデル
■類似理論としてのJD-Cモデル
■離職を減らすには、リソースを増やす
■ハラスメントから離職に至るまでのプロセス
■離職しなかった人の生産性も下がる
■離職を防ぐには、心理面のケアがポイントになる
■「大切にされている」と感じてもらう
■「私は大切にされている」と感じられる対応か?