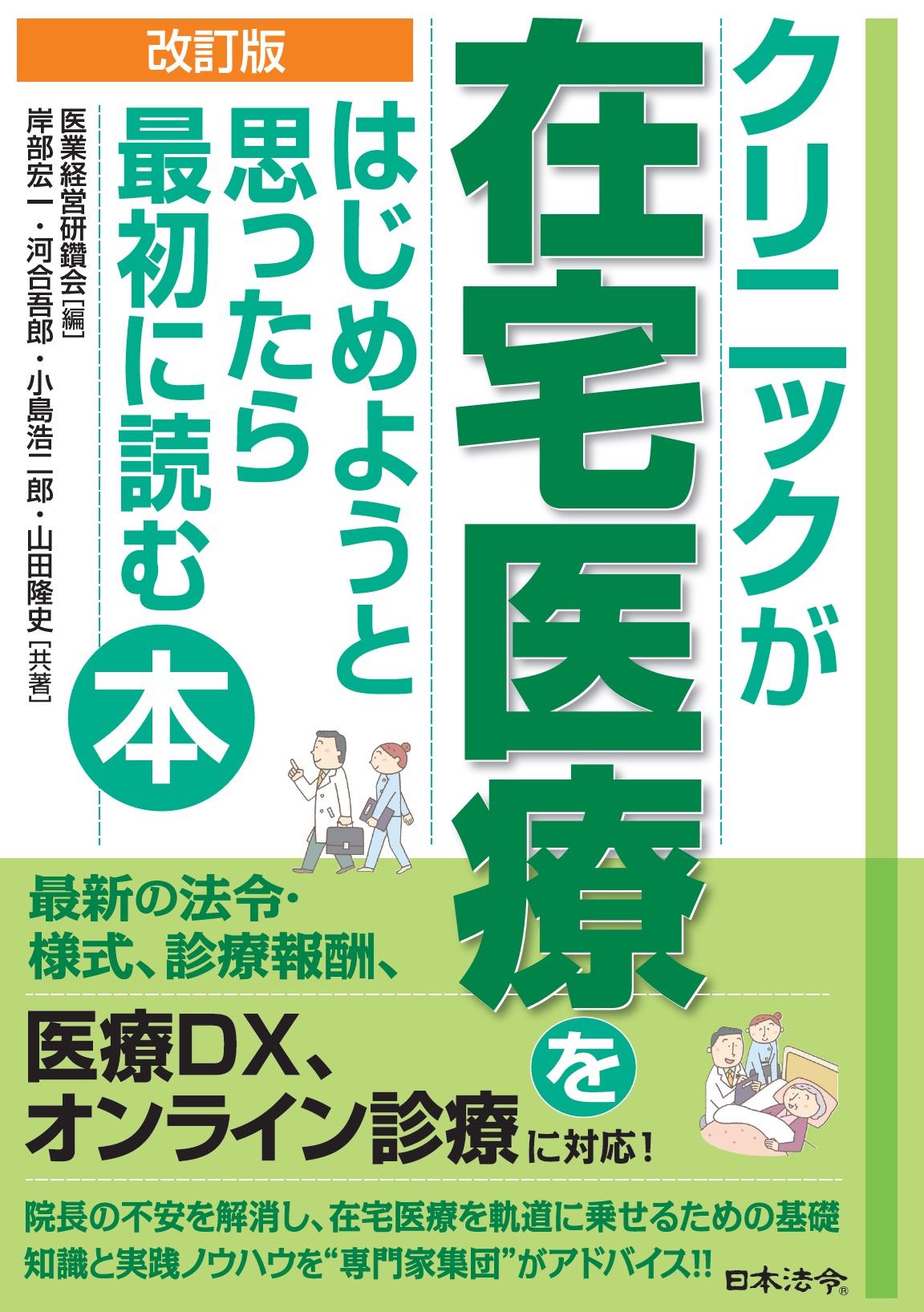商品詳細Merchandise
改訂版 クリニックが在宅医療をはじめようと思ったら最初に読む本
概要
最新の法令・様式、診療報酬に対応!
医療DX、オンライン診療を盛り込んだ待望の改訂版!!
2014年から始まった地域包括ケアシステム構想のなかで目標とされた「団塊の世代」が後期高齢者となる2025年を迎え、その間に2022年と2024年の診療報酬改定を経験し、コロナ後にはコロナ前ほどの外来患者数は戻らず、急激な人口減社会がいよいよ現実の問題となる等、医療を取り巻く外部環境は大きく変化しました。
また2024年診療報酬改定の影響も大きく、2025年春の医療機関の決算を見る限りでは、これまでに経験したことのない経営環境の悪化を感じています。
2040年頃までは増加を続ける「看取り」を病院外でいかに支えるかという点についてはもはや社会問題となっており、かかりつけ医機能を担うクリニックには在宅医療の機能を兼ね備えることが期待されています。
本書はそのような院長向けに、はじめての在宅医療を軌道に乗せるにはどうすればよいかを、事務長経験を持つ医業経営コンサルタント、弁護士、税理士、行政書士の“専門家集団"が解説。いかに現場の負担を軽減し、在宅医療を無理なく進めていくか、具体的にイメージできる内容となっています。
改訂にあたっては、2021年2月の初版発行以降の最新の法令・様式、診療報酬に対応した内容に改めるとともに、今後の在宅医療の場面でも大きな役割を果たすことが期待される医療DXとオンライン診療等について、現時点で判明している情報を可能な限り加えています。
詳細
[目次]
序説 ~法令クリニック2代目院長が、はじめての「在宅医療」を軌道に乗せるまで
第1章 在宅医療の基礎
第1節 在宅医療とは
1.医療の提供を受けられる場所
2.狭義の在宅医療と広義の在宅医療
3.在宅医療の対象
4.往診と在宅訪問診療
5.在宅療養支援診療所
6.在宅時医学総合管理料
7.施設入居時等医学総合管理料
8.24時間対応の問題
9.在宅ターミナルケア、看取り、死亡診断
10.介護保険の居宅療養管理指導
第2節 在宅療養支援診療所とは
1.在支診の施設基準
2.在支診の3つの類型
3.機能強化型の在支診
4.機能強化型在支診の病床あり・なし
5.在支診の施設基準を届ける際に必要なこと
6.在医総管等の届出
7.初診料の機能強化加算
第3節 往診料と在宅患者訪問診療料
1.往診料
⑴ 夜間・休日加算と深夜加算
⑵ 緊急往診加算
⑶ その他の加算
⑷ カルテ記載の注意点
⑸ レセプトに関するアドバイス
2.在宅患者訪問診療料
⑴ 在宅患者訪問診療料の算定要件
⑵ 「通院困難」とは何か
⑶ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)と在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の違い
⑷ 在宅患者訪問診療料1、同2
⑸ 同一建物居住者以外の場合と同一建物居住者の場合の違い
⑹ 在宅患者訪問診療料の加算
(7) 訪問回数による在宅患者訪問診療料の見直し
(8) 同日の往診料と訪問診療料
(9) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の算定要件
(10) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の算定の際のカルテ記載
第4節 訪問診療における診療契約
1.診療契約の内容と当事者
⑴ 診療契約の内容
⑵ 診療契約の当事者
2.診療開始時に必要な文書
⑴ 訪問診療に関する同意書
⑵ 訪問診療に関する説明書兼同意書
⑶ 個人情報取扱等に関する同意書
⑷ その他
3.個々の診療行為に関する同意
⑴ 一般的な診療等に関する同意
4.終末期の診療等に関する同意
第5節 在宅時医学総合管理料等と在宅療養指導管理料
1. 在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施医総管)
⑴ 在医総管の変遷
⑵ 在医総管と施医総管の違い
⑶ 在医総管等の算定の仕方
⑷ 単一建物診療患者数とは(同一建物居住者との違い)
⑸ 在医総管の単一建物診療患者数が2人以上の場合
⑹ 施医総管の認知症対応型生活介護事業所(グループホーム)における算定
⑺ 施医総管の矛盾
⑻ 在医総管の算定例
⑼ 在医総管等の加算
⑽ 在宅療養計画
⑾ 24 時間対応の説明と文書の提供
⑿ 24 時間対応の問題(その2)
2. 在宅酸素療法指導管理料について(在宅療養指導管理料の例として)
⑴ 在宅療養指導管理料とは
⑵ 在宅酸素療法とは
⑶ 在宅酸素療法のカルテ記載
⑷ レセプト上の注意点
第6節 終末期の診療報酬
1.在宅ターミナルケア加算
2.看取り加算と死亡診断加算
3.終末期の対応
4.カルテ記載とレセプトについて
5.死亡した同一建物居住者の訪問診療料
6.がん末期の診療報酬
⑴ がん末期の同一建物居住者の訪問診療料
⑵ がん末期の在医総管等の加算
⑶ 在宅がん医療総合診療料
第7節 訪問看護
1.訪問看護指示
2.要介護者への訪問看護の報酬
3.特別訪問看護指示
4.点滴指示
5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料
6.点滴のまとめ
第8節 介護保険(居宅療養管理指導)との関係
1.居宅療養管理指導とは
2.居宅療養管理指導費
3.居宅療養管理指導費の算定要件
4. 医療機関が介護保険の居宅療養管理指導費を請求するには
5.訪問診療における諸手続きとその手順
6.在宅訪問診療の行い方
第9節 在宅医療におけるICTを用いた連携の推進および医療関連の診療報酬
1.在宅医療DX情報活用加算
2.在宅医療情報連携加算
3.在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
4.往診時医療情報連携加算
5.介護保険施設等連携往診加算
6. 在宅データ訂提出加算
第2章 在宅医療の実践
第1節 在宅医療開始前後の収支シミュレーション
1.クリニックにおける在宅医療導入の必要性
2.従来の外来型クリニックと在宅療養支援診療所
3.訪問診療導入シミュレーションⅠ
4.訪問診療導入シミュレーションⅡ・Ⅲ
第2節 在宅医療に関連した人的問題
1.医 師
2.事務職員
3.看護師
第3節 クリニックによる訪問看護の提供
1.収入面
2.人員配置基準
3.開設主体および開設地
4.開始までの許認可、届出等
第4節 在宅医療に対応した設備等
1.診療所の構造
⑴ 患者エントランスと別に職員用玄関(裏口)を設ける
⑵ 裏口を入ってすぐのところに独立の小部屋(できれば複数)を設け、以下の用途とする
⑶ 平面図上で「診療所」「附帯事業所」の区分けを意識して設計(ゾーニング)
⑷ 訪問診療割合が95%以上の「主として往診または訪問新診療を実施する」
⑸ 上記以外の在宅療養支援診療所
2.建物以外の設備投資
3.自治体等の支援の活用
第5節 多職種連携
1.多職種連携の問題点
⑴ 多職種連携における医師の問題
⑵ ICT ツールの利用
⑶ 医療情報発信の問題
2.サービス担当者会議
⑴ サービス担当者会議とは
⑵ サービス担当者会議の進め方
⑶ サービス担当者会議での検討例
⑷ 医師のサービス担当者会議への参加問題
3.在宅患者の集患と多職種連携
第6節 移動手段
1.訪問先への移動中の事故
2.自転車事故の法的責任
⑴ 刑事上の責任
⑵ 民事上の責任
3.任意保険
⑴ 自動車保険
⑵ 自転車保険
⑶ 医師賠償責任保険
4.移動に使用する車両
⑴ 移動コストの負担者
⑵ 駐車禁止除外車両
第7節 終末期における対応・問題
1.総 論
2.終末期における診療等
3.終末期における診療等に関する同意
⑴ 患者本人に十分な判断能力がある場合
⑵ 患者に十分な判断能力がない場合
4.施設への訪問診療の場合
5.がん患者の訪問診療・看取り
⑴ 緩和ケア
6.書類(死亡診断書等)の作成
第8節 診療情報の開示等
1.概 要
2.個人情報保護法等について
3.診療中(患者生存中)の開示等について
⑴ 個人情報(個人情報保護法2条1項)
⑵ 要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)
⑶ 利用目的の特定および制限(個人情報保護法17 条、18条)
⑷ 利用目的の通知等(個人情報保護法21 条)
⑸ 個人情報の適正な取得(個人情報保護法20 条)
⑹ 個人データの第三者提供(個人情報保護法27 条)
4.診療後(患者死亡後)の開示等について
第9節 毎年の届出・報告事項
第3章 在宅医療の制度と将来
第1節 歴史的経緯
1.死亡場所の変化
2.増え続ける社会保障費と入院医療費の削減
3.患者意識の変容と経営的視点
第2節 在宅医療の供給体制
1.これまでの経緯
2.全国的傾向
3.地域ごとの状況
4.都道府県の地域医療計画
第3節 制度的誘導
1.診療報酬による参入誘導とその後
2. 地域包括ケアシステムをはじめとした在宅医療に関する国の施策
3. 地域包括ケア体制のなかでの在宅医療の役割
4. 新規開業に際しての在宅医療への参入の意向確認
第4節 不適切事例の増加
1.朝日新聞による訪問診療不正報道
第5節 かかりつけ医と在宅医療
1.診療報酬上のかかりつけ医機能
2.地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医
3.地域包括診療料
4.2014 年および2016 年以降の診療報酬改定
5.初診料の機能強化加算
第6節 現場の負担解消に向けた取組事例
1.在宅副主治医制(柏モデル)
2. インターネット回線を用いたカルテ情報共有
3.「 ベッドサイドノート」を用いた多職種との連携
4. グループでのオンコール当番制による訪問診療
第7節 オンライン診療と在宅医療
1.遠隔診療・オンライン診療の経緯
2. 在宅医療におけるオンライン診療の診療報酬
3. 在宅医療におけるオンライン診療の可能性
(1) 訪問診療とオンライン診療の組合せ
(2) ICTを活用した遠隔死亡診断
(3) DtoPwithN
(4) その他在宅患者に対するICTを活用した多職種連携